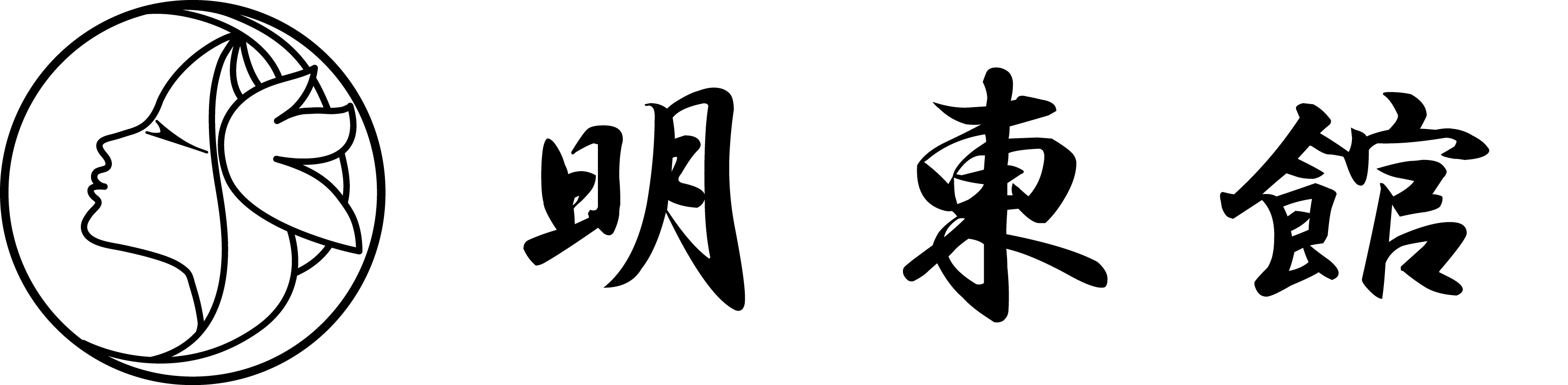「西門から帰ろうか」
私たちは顔を見合わせて、掛け声とともに、学生カバンを西門の向こう側に放り投げます。
続いて、セカンドバッグ。
最後に、セーラー服のスカートにも構わず、一気に西門をよじ登って、向こう側へと飛び降ります。
Mちゃんと私が通っていた高校は、18時に西門は閉じられ、施錠されてしまいます。
私たちの帰宅先は、西門からすぐの町内で、正門から下校するのは、ほんの少し遠回りになるのです。
バドミントン部の部活が終わって、18時過ぎ。
お腹を空かせた私たちは、ほんの少しの遠回りをショートカットするため、西門をよじ登って飛び降りるのでした。
私たちは、保育園から、小・中・高校一緒で、部活も一緒の幼馴染。
帰り道もずっと一緒だったけれど、高校2年生の3学期、私が部活をやめて以降、学校の「廊下ですれ違うだけの関係」になりました。
バドミントン部を途中でやめた私と、最後まで成し遂げたMちゃん。
曖昧な物言いをする私と、意思ある発言をするMちゃん。
何となく疎遠になったまま、卒業式の日にも、私たちは顔をあわせたかどうかわかりません。
高校卒業後、彼女は東京の大学に進学し、地元に残った私は、彼女の活躍ぶりを風の便りで知るだけでした。
もう、彼女と西門をよじ登って飛び降りることもないのだろう、そもそも彼女は忘れてしまってるだろうと、学校のそばを通るたびに、ふと思ったりもしました。
しかし、私たちは32年ぶりに同窓会で再会し、私はそこで、彼女が西門でのエピソードを覚えていることを知りました。
彼女は、西門の写真をみて
「当時はフェンスではなく、木製の扉で、階段を登りつめたところに門があった」ことも言い当ててくれました。
「今のフェンスのほうが、登りやすそうだね」
Mちゃんの言葉に
私は心から笑うのです。
そして、16歳の私たちが、西門をよじ登って飛び降りるとき、どんな表情だったか回想するのです。
彼女は笑顔だった。
今の私は
それだけで
じゅうぶん幸せな気持ちになれて、そんな彼女の笑顔を見ることができた自分も幸せだったと思うのです。
そして、彼女といるときの自分が好きだったことに気付くのです。
私の、曖昧な物言いは協調性という阿(おもね)り。
彼女の意思ある発言に、私は憧れていたのだとも気付くのです。
私は
「ライバルだと思っていても、相手にされなければ、ただの憧れになる」ことを認めたくなかった。
少女期の闇を悟られたくなかった。
それに気付くまで、こんなにも長い年月が必要でした。
西門を飛び越えることは、私が大人になるための通過儀礼だったのかもしれません。
西門は、長くせき止めていた想いをあふれさせ、飛び越えて、私達を再び笑顔にしてくれる場所となったのです。
Mちゃんとは、また西門で会うことを約束しました。
そして
その約束が果たされなかったとしても
誰かの笑顔を想い
幸せになれることを知った今
私は、それもいいかなと思うのです。
『スタンド・バイ・ミー』恐怖の四季 秋冬編・著者:スティーヴン・キング・訳者:山田順子・発行所:株式会社 新潮社 (1987年)昭和62年3月25日発行
映画版『スタンド・バイ・ミー』・提供:コロムビア映画会社・編集 発行:松竹株式会社事業部 (1987年)昭和62年4月18日発行