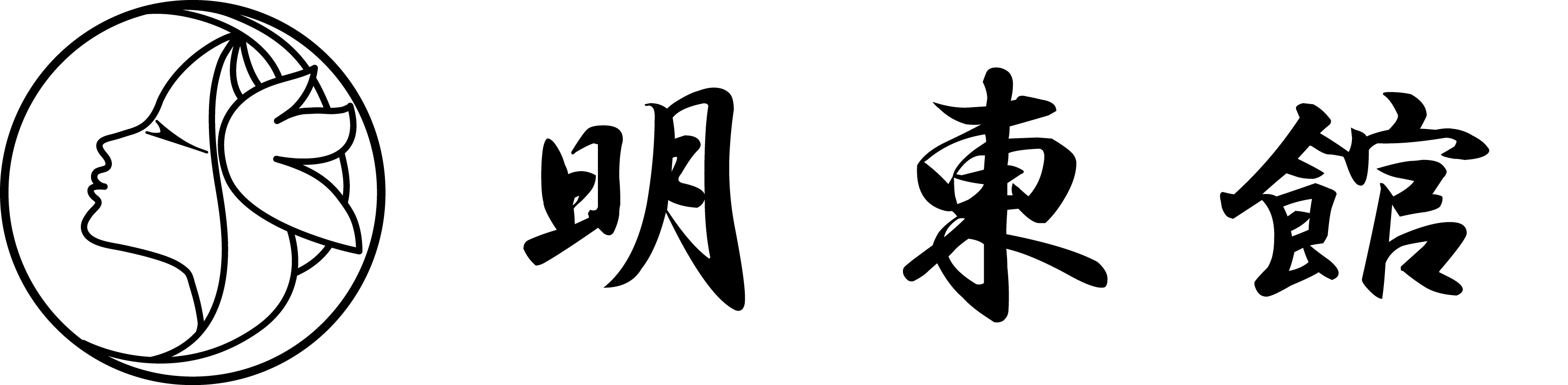「目の前で起きている出来事だけを、冷静に伝える難しさ」
共同通信社ラジオテレビ局に所属されていたF氏は語られます。
1982年(昭和57年)2月8日未明、「すぐ現場にラジオ中継に行ってくれ」と、局長に指示され向ったのは、千代田区永田町ホテル・ニュージャパンの火災現場でした。
現在のように、スマホで簡単にホテルの規模・床面積・階数・部屋数・宿泊者数が検索できる時代ではありませんでしたので、情報発信の基本である「数字」の情報すら、中継中に正確に把握できなかったそうです。
原稿もない。
情報もない。
ラジオ中継は始まっている。
本来は編集部所属だが、急遽アナウンサーとして喋らなければならないプレッシャー。
新しい情報が入ってこなくて、時間だけが経過する。
ラジオという画像がない媒体では「ご覧のように」と、ビジュアルに頼れない。
同じ内容を繰り返し喋るだけではなく、何か新しい情報を発信しなくてはならない焦り。
そうした状況のなかで、F氏は「目の前で起きている出来事だけを、冷静に伝える」ことに集中しながら
個人の意見
感想・感覚
思想・イデオロギー
脚色
事故に関係ない情報
それらを排除した、中立のアナウンスを心がけたそうです。
実際に、当日の現場中継の記録テープを聞かせていただきましたが、混乱しているであろう現場のなかで、興奮も動揺もせず、静かにアナウンスする声にF氏の中立性を感じました。
しかし、いくら中立を心がけても、個人の私情は入ってしまうそうです。
例えば《木が倒れている》という出来事の描写は「火災の悲惨さ」の記号になってしまいます。
《木が倒れている》は、現場の状況を説明するために必要かと思われますが、「何を根拠に悲惨とするか」の定義に混乱を招きます。
「木が倒れたくらいで済んだ」と発信するか
「木が倒れるほどの衝撃だった」と発信するか
この時点で、個人の感覚や感想が入ってしまいます。
「悲惨の定義」は
F氏のような戦時中生まれか
新人記者の戦後生まれかの経歴で違ってきますし
個人の経験値・育った環境によっても違ってきます。
生身の人間が記事を”発信”してゆく以上、この不公平さは無くなりません。
同じ事件・事故を取材しても、報道記者によって全く印象の違う記事になる理由です。
また、《木が倒れている》の「木」を
「大きく繁っている欅の木」なのか
「庭園にある観賞用の松の木」なのか
「エントランス生垣の椿の木」なのか
詳細に説明し過ぎると、印象操作にあたります。
これもまた、”受信”する側の視聴者・読者が生身の人間である以上、「欅」「松」「椿」からイメージするものが違います。
「椿にこだわりや愛着がある人」にとって、事故の印象・心象が格段に悪くなる可能性があります。
あるいは、事故の関係者やご遺族にとって「椿」が「悲惨」の記号とセットになり、トラウマになる可能性もあるからです。
記者の発言する「記号」が何とセットになるかわからない。
だから
《木が倒れている》ことを記事にしないことが中立。
私は非常に驚いたのですが、なるほど大いに納得しました。
私に記事を書かせたら
「悪魔の所業」
「投獄に値する」
「厭わない覚悟を持て」などと個人的な感情が入りすぎて、もはや新聞記事ではなくなるでしょう。
そういった経緯で、私は
「目の前で起きている出来事だけを、冷静に伝える」ことに憧れるようになりました。
それでもお客様に向きあい
理解しようとするとき
怒りや悲しみに感化され
感情が揺れて
私情を挟んでしまいそうになることもあります。
「目の前で起きている出来事だけを、冷静に伝える難しさ」
感情に揺さぶられないよう、冷淡であることの難しさ。
中立であることの難しさ。
日々、葛藤しながら
戒めながら、お客様と向きあうよう心がけてゆくだけです。
それだけです。