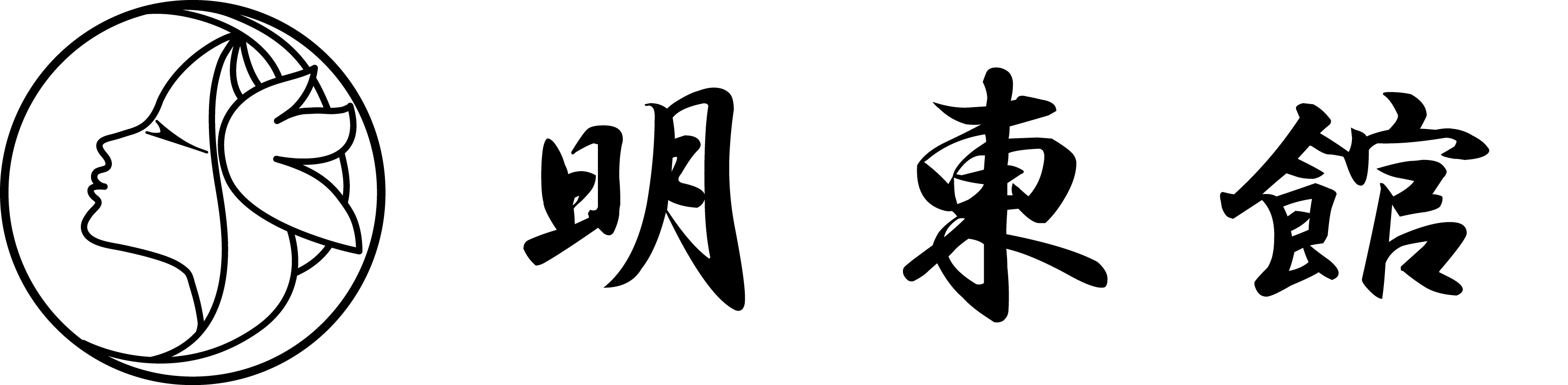『 秋風一夜百千年 』
こうして秋風の中であなたと過ごす一夜。
それは私にとって百年にも千年の歳月にも値するものです。
一休宗純 (1394〜1481年)『狂雲集』
1470年摂津国。住吉大社神宮寺新羅寺本堂・薬師堂で、禅宗・臨済宗派の 一休宗純は、盲目の旅芸人・森女(しんじょ)に出会いました。
このとき一休は76歳、森女は20代と伝えられています。
森女は弟子として酬恩庵(京都府京田辺市薪地区)に迎えられ、周囲の誹謗中傷をものともしない一休の寵愛を一身に受け、一休臨終のときまで添い遂げました。
一休は、森女との日々を濃密な艶詩にして『狂雲集』に綴り、宗教的基盤に立つ求道的なほかの作品とは相矛盾する観念や価値観を同時に共存させました。
応仁の乱(1467年〜1477年)の主戦場となった京都は、10年もの長きにわたる戦で焼き尽くされてしまいました。
戦の爪痕は深く、政治の混乱が続く都では、治安の悪化・疫病の流行・天災に襲われ、「必ず明日の日がある」ことを約束できない状況にありました。
そのような時代背景を想像すると
『秋風一夜百千年』という短い言葉のなかから、一休の切なる想いが伝わってきます。
艶詩からは、一休が森女と過ごす時間をどれだけ愛おしく大切にしていたかが伝わってきます。
そこには、森女と過ごす時間が、儚く消えてしまうのではないかという一休の怖れも読み取ることができます。
一休は、ふたりの未来を想像したとき、双方のどちらかが「不在」になるときが、明日にでも訪れることを覚悟していたのかもしれません。
目の前に愛する誰かを確かめて、言葉を交わし、触れることができるのは、「どれほど稀有で貴重な時間であるか」ということを説かれたのだと、私は想像しています。
「この一夜は千年にも値する」と思えるほどの人とめぐり合えたなら、その人の人生は幸せだったのではないかと思うのです。
そして、誰にも「必ず明日の日がある」と約束できないならば、今、目の前にある人を最期に会える人とも思えるのです。
人生は、時間は流れているのではなく、その一瞬、一瞬が人生をつくっている。
『秋風一夜百千年』は時代を超えて、そのメッセージを今に伝えてくれているようです。
『日本歴史大辞典』発行所:株式会社 小学館 2000.07.10
「狂雲集」解説:朝倉 尚
一休宗純 (いっきゅうそうじゅん)
『秋風一夜百千年』(しゅうふういちやひゃくせんねん)