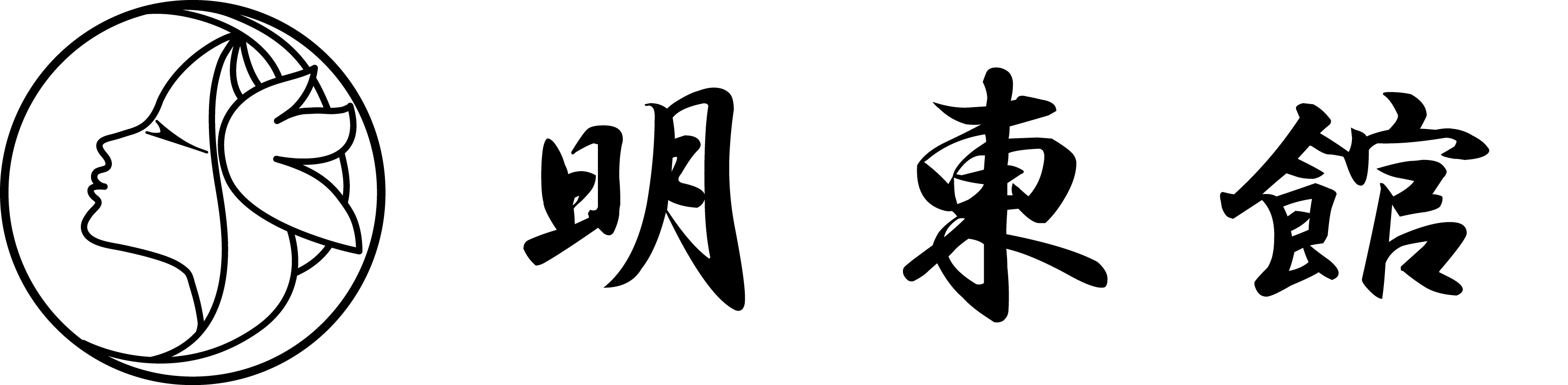「別れる男に花の一つは教えておきなさい。花は毎年、必ず咲きます」
「別れる男に花の一つは教えておきなさい。花は毎年、必ず咲きます」
あるエピソードをお伺いしてから、私はこの言葉の解釈が全く変わりました。
Aさんのお祖父様は、出張で上京するたびに「椿」の苗を持ち帰り、自宅の庭に植えて大切に育てられていたそうです。
東京から自宅までの長い道中、新幹線から在来線への乗換えや待ち時間を考慮すると、明らかに荷物になる椿の苗を、なぜお祖父様がわざわざお持ち帰りされていたかは語られなかったそうです。
お祖父様が他界された後、誰も理由を知らないまま、今はAさんが椿のお世話をされているそうです。
私はAさんのお祖父様の「椿」の物語から
「別れる男に花の一つは教えておきなさい。
花は毎年、必ず咲きます」
という言葉を思い出しました。
別れる男性に「花の名前」を女性が教える。
花の季節になって、男性が、その花を見つけたときに女性を思いだす。
Aさんのお祖父様のエピソードをお伺いするまで、私はこの言葉をある種の呪いのように感じていました。
「私を忘れないで」と。
忘れ去られる恐怖から、必死で自分を想起できるものを誰かに伝えようとするイメージでした。
しかし
Aさんのお祖父様のエピソードからは、椿にまつわる何かを、優しい気持ちで懐かしむ様子が伝わってきます。
そこには
手紙
写真
プレゼントなど
何か形あるものではなく
何も形に残らない
わずかな時間だけ
ひととき咲いて、散るだけの花。
忘れ去られる恐怖ではなく
一瞬、思い出してもらえる幸せ。
それがこの言葉の真意だったのではないかと思えるようになりました。
別れのシチュエーションは様々で
「まだお互いに愛が残っているにもかかわらず別れを余儀なくされたふたり」
「どちらかの愛が冷めたふたり」
「横恋慕」
「もともと何の約束も交わされていなかったふたり」
それぞれに物語があります。
そこに
悲しみ
虚無
嫉妬
焦燥
絶望があったとしても
それでも
他の誰でもない
「その人との間でしか芽生えなかった感情」ならそれらは財産なのかもしれません。
別れの痛みでさえ
その人に出逢えなければ
知ることもなかった感情。
それならば、せめて
別れたその人の幸せを願う
慈しみの心を持てるようになりたいと思うのです。
「誰かの心に住み続けることを願うのではなく、私が忘れないだけでいい」
Aさんのお祖父様の椿を大切にされる姿からは、そのような慎み深い佇まいが浮かんできます。
Aさんのお祖父様に何があったかは、私もわかりません。
ただひとつ言えるのは、「椿」がもし誰かを想起させるものならば、お祖父様もその誰かも幸せだったのだと私は思うのです。
ほかの誰も知ることのない、ふたりだけのエピソード。
花だけが知っている。
そんな静かな情景が浮かんできます。
そうして私は、花の名前を誰かに教えることはなくなりました。
花の名前よりも、ただそこに存在していることが愛おしく思えるのです。
川端康成 1899年(明治32年)-1972年(昭和47年):『掌の小説』「化粧の天使達・花」1971.03.15・新潮社