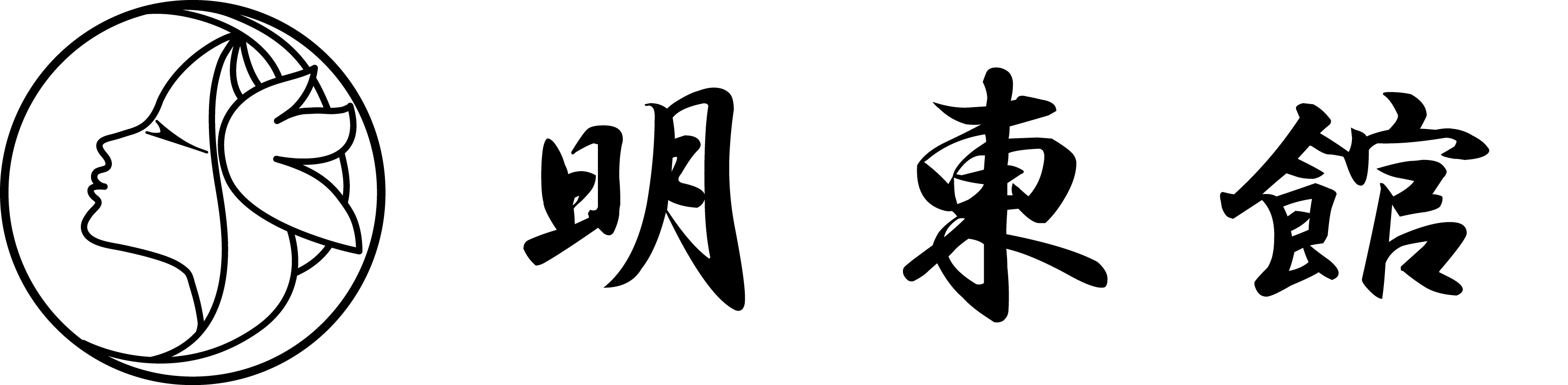「シャンペンだけが人生だと思う?」
村上龍 氏の小説
『テニスボーイの憂鬱』で
主人公の青木へ、不倫相手の吉野愛子が問いかける台詞です。
青木は
既婚
ステーキハウスのオーナー
家庭を大切にし
人脈も広く
テニスプレイヤーとしても充実している。
吉野愛子は
独身
売れないモデル
独り暮らしのアパート
部屋の窓に黒い紙を貼り
冷蔵庫の牛乳を腐らせる生活。
吉野愛子は
未来の見えない不倫関係に待ちくたびれて
「青木を幸せにしているのは私ではない」
と悟り、青木の前から去ってゆきます。
青木は
冒頭の問いかけについて
「シャンペンが
輝ける時間の象徴だとすれば
キラキラと輝ける自分を示し続ける自信がない時
それはひとつの関係が終わる時を意味する」
と無常の答えを導きだします。
『テニスボーイの憂鬱』が発表された1985年(昭和60年)は、日本電電公社がNTTに民営化され、株式市場のあらゆる銘柄は高騰し、日本がバブル期に突入した時代です。
カタカナ職業を指す『業界くん』という造語も生まれ
華やかで
洗練された
輝けるものに価値があると、扇動された時代です。
10代の私は
キラキラと輝けるものに
憧れを抱きつつも
畏れも感じてもいました。
私は、その未熟さゆえ
「キラキラと輝ける自分を示し続ける自信」という表現を
若さ
容姿
メイク
ファッション
装飾品
バッグ・靴
業種
車
など、外見を粉飾するイメージとして解釈していました。
しかし、40年の時を重ね、改めて『テニスボーイの憂鬱』を拝読し、「キラキラと輝ける自分を示し続ける自信」とは、外見ではないことに気付きました。
そのきっかけは、作品中、何度も登場する公衆電話にあります。
1985年当時『公衆電話』は日常のアイテムで、特別注視していませんでしたが、作品の中で公衆電話が、印象的なかたちで何度も登場します。
『テニスボーイの憂鬱』の時代は、携帯電話が普及していなく、不倫相手と連絡をとる手段は、主に公衆電話しかありませんでした。
ひたすら公衆電話を探す青木。
ひたすら固定電話の前で待つ吉野愛子。
吉野愛子は
青木の幸せそうな姿は
自分の影響ではないと
無力感を持ちはじめます。
青木は
吉野愛子の不幸せそうな姿は
自分の影響だと
無力感を持ちはじめます。
ふたりはお互いに
「自分の力で、もう、この人を幸せにできない」と感じたとき、去ることを決意します。
逆説的に
「キラキラと輝ける自分を示し続ける自信」=「自分の幸せそうな姿を相手に見せる」ことができれば、ふたりの関係は継続できたとも解釈できます。
「自分の力で、この人を幸せにできている」と感じ続けるなら、人は去ってゆかないと暗喩しているようです。
不倫関係を継続するためにできることは
自分の幸せなそうな姿を、相手にみせるだけ。
幸せでもないのに
幸せそうな姿はできないと思えたなら、終わり。
スマホが普及した現在でも
不倫の恋人たちの姿は
『テニスボーイの憂鬱』の時代から、実は変わっていないと感じます。
ひたすらLINEを待ち続ける女の子たちに、私は吉野愛子の姿をみるようです。
『テニスボーイの憂鬱』から発信されたメッセージは、現代でも普遍的なメッセージとして伝わってきます。
シャンパンを、吉野愛子に語らせ
腐った牛乳で、吉野愛子を語る。
不倫に介在する光と闇のコントラストを、村上龍氏は見事に描かれています。
不倫関係で
「自分の幸せそうな姿を相手に見せる」ことに疑問を覚えたなら、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
『テニスボーイの憂鬱・上巻』『テニスボーイの憂鬱・下巻』1987年(昭和62年)10月25日第一刷発行・著者:村上龍・発行所:株式会社 集英社